COVID-19パンデミックで日本の医療が危機的状況の中、二期6年会長を務められた沢石由紀夫先生が令和6年12月をもち退任されました。それに伴い、先日の幹事会で私が引き継ぐ事となりました。自分としては、次世代への繋ぎの役割と心得ている次第です。てんかんとの付き合いは35年と長いものの、学会活動にはあまり携わって来なかったので至らぬ事も多いかと存じますが、会員皆様のご指導を頂き精一杯やる覚悟です。
人口減少が将来の日本経済の最大のリスクだと指摘されたのはもう10年位前になりますが、今やそれが明らかとなり、経済に限らず日本そのものの存続に係わる問題となっています。地方では既に人口流出と高齢化が現実となっていますが、医療に関して言えば患者減より先に従事者減が加速し、医療体制がいつ破綻してもおかしくない状況です。そのような中で、高度に専門的、先進的な医療の追及は必要ですが、多くの患者さんにとっては「自分にとって最も良い医療をどこに居ても受けられる」事の方が重要です。我々は専門家として、自分たちが診療や研究で得た知見をいかに普及させ、一人でも多くの人がその恩恵に与れるように努力するのが肝要と考えます。
これからは、どの学会でも専門志向の会員が集まるだけでは成り立たなくなります。てんかん学会も(特に地方会は)てんかんがcommon diseaseであり、片頭痛と同じように日常診療で診る疾患であると広めて行かなければならないと思います。てんかん診療のボトルネックが診断である事は事実ですが、診断はほぼ問診で付けられるので、ファーストラインならてんかん確度80%で副作用の無い薬剤での治療を開始する等の誰でも使えるパッケージを用意するのも悪くはないでしょう。かかりつけ医であれば、第一選択薬が奏効しなければ紹介、で良い訳です。さもないと、我々の知らない所でてんかん患者さんの多くが診断も付けられず治療も受けられないまま放置されるか、不適切な治療を受け副作用に苦しむ事になりかねません。その一方で、大脳の機能性疾患としてのてんかんが、より多くの(若い)医師の興味を引くような教育も継続して行かねばなりません。てんかんは何科が診るか、では困るのです。大脳機能障害に関わる全ての職種がてんかんを理解する事が大切です。譬えれば、てんかんという絵のジグソーパズルを、ピースの大きさ(数)を変えて提供するようなものです。我々は1,000ピースですが、かかりつけ医は10ピースで良いでしょう、となる訳です。ピースの位置関係を大雑把に理解すれば10ピースならすぐ作れる。出来上がる絵は同じです。
継続可能な学会であるために何が必要か、会員の皆様と一緒に考えて行ければと考えています。
日本てんかん学会東北地方会 会長 宇留野勝久
国立病院機構山形病院 院長
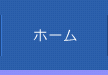

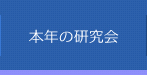
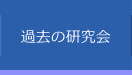

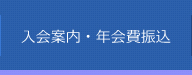

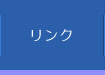

 日本てんかん学会
日本てんかん学会 国際てんかん連盟
国際てんかん連盟